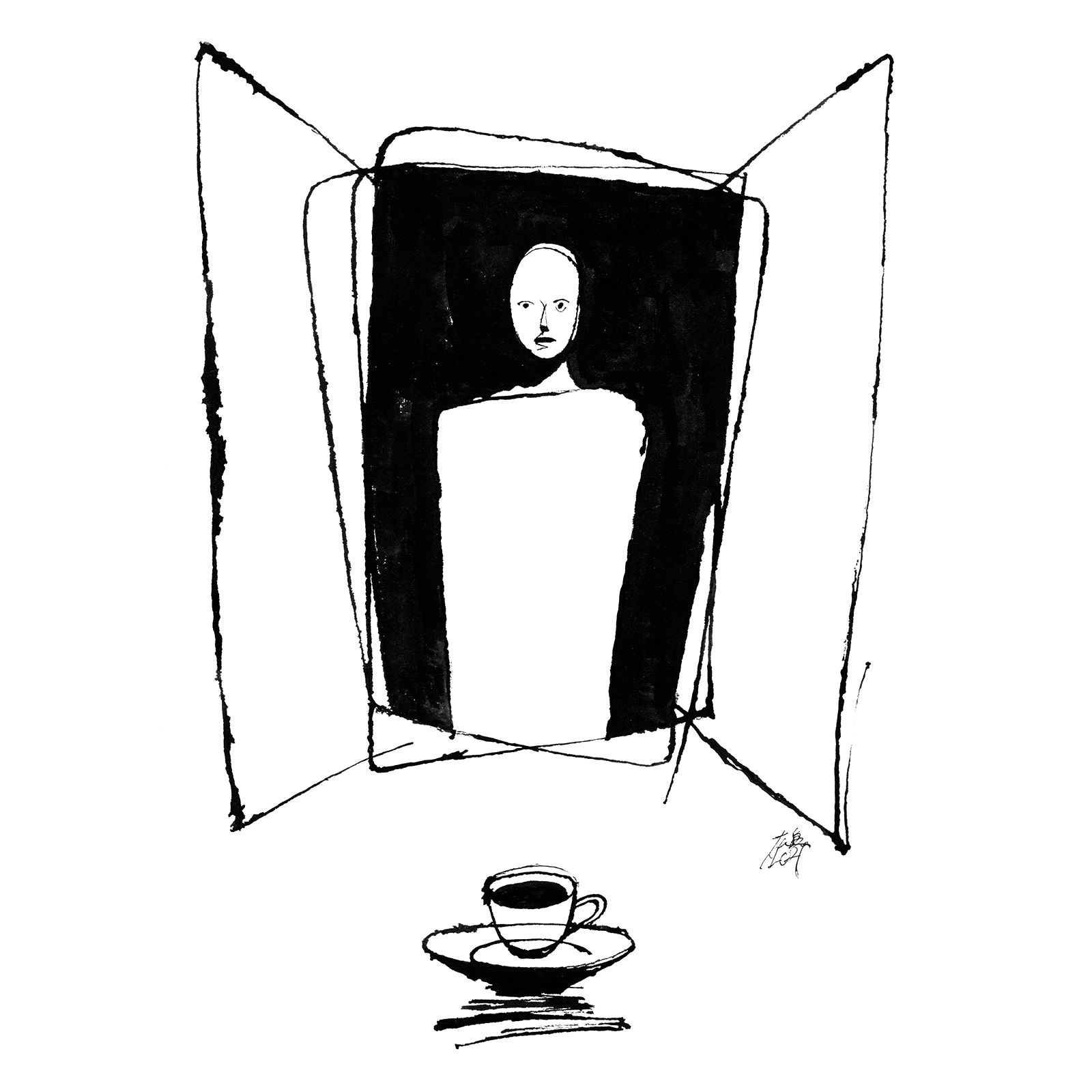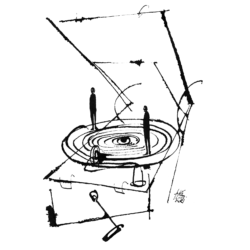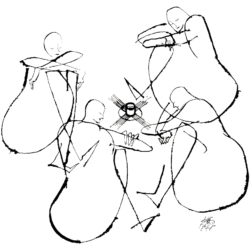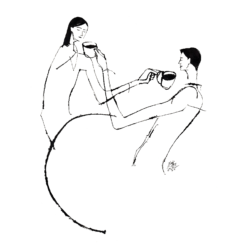「珈琲の門がひらく日」
珈琲豆屋の友人がこんなことを言っていた。
ある昼下り、八つか九つくらいの男の子が「コーヒーください」と店に入ってきた。友人は焙煎家で、店でローストしながら豆を売り、配達もこなし、手があいていれば1杯270円でドリップまでして、それをご近所さんが飲んで帰る。町にまっすぐ根を下ろした、近くにあると心底助かるような店の主だ。
少年が求めたのはカップのブラックコーヒー。
20年 珈琲を生業にしてきた友人にとってしても、小銭を握りしめた子供がひとりで珈琲を飲みに来るなど初めての出来事で、面食らった勢い「おまえ、小学生やろ?」と追い帰してしまった。 が、 帰したあとからすげない態度を反省まじりにふり返り、しばらく釈然としない気持ちが残ったのだと語った。
小学生が珈琲を飲んでならない法はないが、興奮して眠れなくなっては気の毒である。
このいっぷうミステリアスな話を聞き終えて考えたのは、スパイスを強烈にきかせたカレーを涼しい顔で食べるインド人、真っ赤な唐辛子エキスをしたたらせたキムチを頬張る韓国人のことだった。刺激物をおいしいと感じる味覚はいつ、どう成熟するのか。
聞いたところだと、韓国では小さなうちから水キムチをせっせと与え、辛さに慣らしてゆく。給食もむろんキムチ。日々の鍛錬のたまものとして、辛い/酸っぱいが旨味もろとも快楽に感じる舌を得る。インド人とカレーの関係も同様だろう。
フランスの家庭では、子供も朝食時にカフェオレをたっぷりと飲む。珈琲とミルクは同量。成長につれ苦味を欲するバランスが増えてゆき、濃いエスプレッソに着地するというパターンがお決まりだ。
日本の場合、朝ごはんはどうしても白飯にお味噌汁が推奨されるし、ランドセル姿でカフェオレを飲み干す子供の話は聞かない。とすると、大人になった今でこそ朝一杯の珈琲を目当てにベッドからおりる珈琲ラバーも、家庭で「徐々に」苦味に慣れたというよりかは、ある一点で「珈琲の門がひらく」経験をしたのではないか。
琥珀色の鐘が鳴り、目がぱちんと冴えて、その日をさかいに珈琲の虜となる。もはや珈琲のない人生なんて考えられない…。
と言うのも自分がそんな経験をしたからだ。
あれはK町で映画を見た帰りのこと。19歳。K町は、都心ではおよそかかならい酔狂なタイトルを観せる映画館がいくつかあり、好んで通っていた。確かヴェンダースの『ことの次第』のあとだ。へんな気分になって、いつもなら紅茶を頼む喫茶店で「珈琲ください」と口をついた。ガラスケースに並ぶハンドメイドケーキが常時6種類はくだらない、英国ふうの正調な店。創業は古いが、ヘリンボーンの床板をコツコツ小気味良い音を立て歩き回る給仕は皆、若かった。私を珈琲の国へ招き入れた一杯をドリップしたのも やはり若く、あまつさえ女性であった。皮膚を切りそうに糊のきいたホワイトシャツ、体にぴたりと沿う黒いベストを着た彼女の珈琲は、今思うと紅茶寄りの爽やかさがあった。口のなかに春が訪れたような、甘くうららかな余韻の残る中煎りで、最後の一滴までミルクや砂糖が欲しくならなかったのは、初めてのことだった。
「ねぇ、どんな感じの子だったの? その珈琲ボーイ」
私は友人に尋ねた。
「…何だか かわいげのない子だったんだよ」
少年は既に官能の味覚が開かれていたのだろうか。いや、そうではあるまい。きっと大人のポーズを真似てみただけなのだ。家に珈琲の薀蓄を語るお父さんがいたのかも分からない。
分かっているのは、少年がふたたび友人の店を訪れてはいないこと。訪れるとしたらもう30センチは背を伸ばし、ホロ苦い経験を済ませてからだろう。