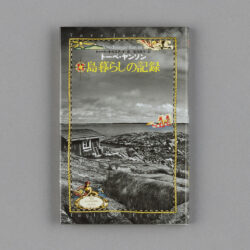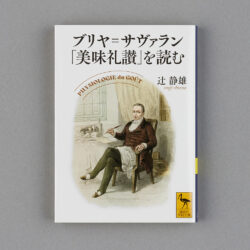コーヒーもう一杯
コーヒー一杯でどれくらい長居したか。団塊世代の人たちに、当時のジャズ喫茶やロック喫茶の話をうかがうと、ある種の自慢話のようなニュアンスさえ含ませながら、必ずといっていいほどそういったニュアンスの話を口にする。永島慎二に代表されるような、高度経済成長期の喫茶文化を刻印した漫画を開けば、コーヒーカップはテーブルに鎮座したまま、そこに長居することができる免罪符のようにおざなりに描かれている。
一杯のコーヒーが若者たちの貧しさを象徴しているのかといえばそうではない。アメリカのロードサイド・ダイナーのスタイルを真似、バブル期以降地方都市の郊外を席巻したファミリーレストランには「ドリンクバー」というシステムがつきものだ。本場のダイナーのコーヒーがお代わり無料であることを真似たサービスには、炭酸飲料や紅茶など実に多彩なドリンクが取り揃えられている。そのファミレスのボックス席に入り浸る三人の若者を定点観測的に描き2000年代初頭の文化風俗を細やかに記録した漫画『THE3名様』には、無料であるにも関わらず、彼らがコーヒーをお代わりする様子はまったくといっていいほど描かれない。大体誰がダイナーで紅茶や炭酸飲料をお代わりするだろう?
それに対して、フィクションの中のアメリカ人たちは実に多くのコーヒーを飲む。ダイナーで、ポーチで、ベッドサイドで、カップには立て続けにコーヒーが注がれる。アメリカ人の胃が頑健なのか、それともアメリカンコーヒーが薄味なのか。
片岡義男の初期作品に「六杯のブラック・コーヒー」という短編がある。東海岸から西海岸、およそ3000マイルを際限なく行き来する長距離ドライバーの目を借りて、広大な北アメリカのハイウェイで遭遇する生と死をスケッチしてた名編だ。ドライバーには繰り返し訪れるトラック・ストップがある。馴染みのウェイトレスは束の間の恋人となり、彼らの好みのコーヒーを好みのタイミングでサーブする。ジュークボックスでカントリー・ソングをリクエストしたときが六杯目、最後の一杯の合図だ。
彼らにとってコーヒーは死がまとわりつく長距離運転を乗り切るための気付け薬でなければならないのと同時に、束の間の逢瀬を楽しむ穏やかな時間を演出するものでなくてはならない。なんでもないが飽きがこないし、次の一杯に手が伸びる。そういう珈琲を彼女たちは淹れることができるのだ。入魂の一杯もいいが、飽きのこない味わいが日常にあればもっといい。